家事代行サービス依頼前に知っておきたい盗難対策

家事代行サービスを使ってみたいけど盗難が気になる
このような悩みを解決する記事になります。
なぜならうちでも実践しており、これまで一度も盗難にあっていないからです。
記事前半では実際のトラブル体験や未然に防ぐ方法を紹介、後半では対処法を解説します。
これから紹介する「盗難未然に防ぐ方法」を実践すれば、不在時の家事代行サービスも気持ちよく利用できますよ!
家事代行のトラブルについてはこちら
≫ 【※注意】家事代行でよくあるトラブルと対処法を解説
家事代行の盗難対策
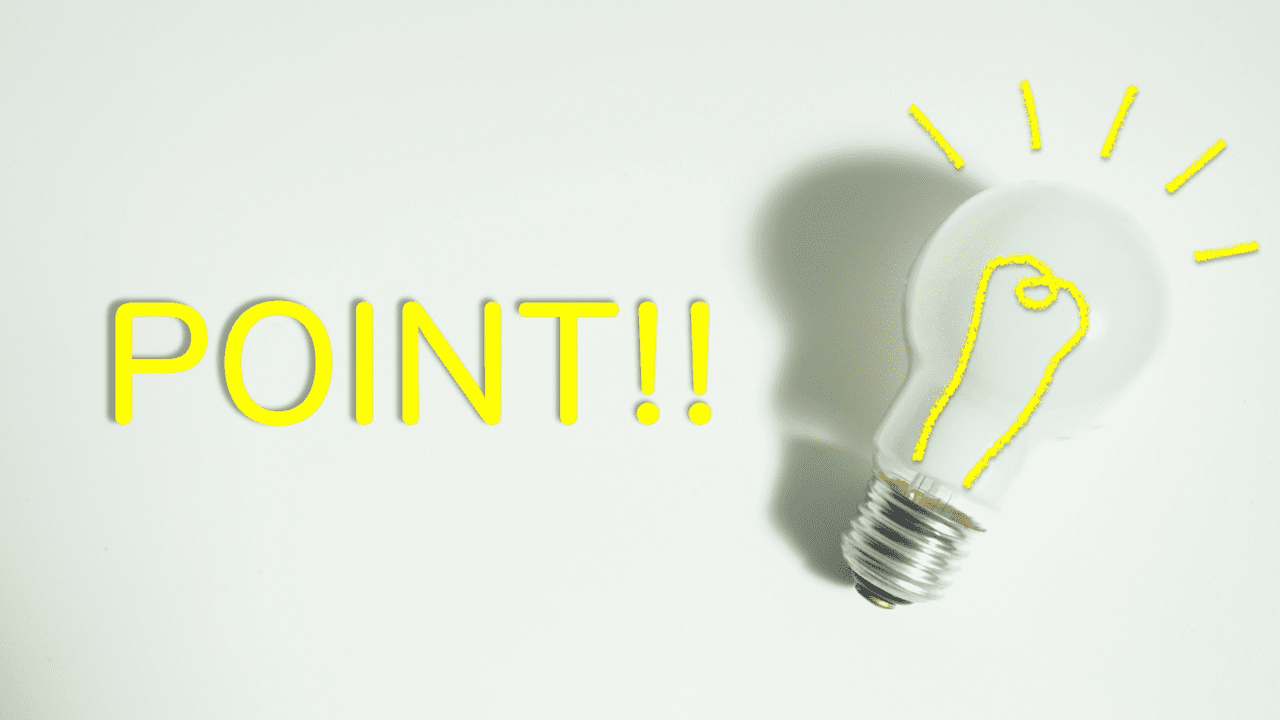
それでは、家事代行の盗難対策を紹介します。
家事代行サービス初利用の人はもちろん、使い慣れている人でも参考になるはずです。
- 契約内容や料金をしっかり確認
- 掃除する場所を限定
- 作業前に部屋の写真を撮る
- 在宅する
- 貴重品は金庫へ入れる
- 防犯カメラを設置
- 依頼する業者の数を絞る
- スタッフは指名する
- はじめはお試しプランにする
契約内容や料金をしっかり確認
依頼者とスタッフ、お互い勘違いしないよう契約内容や料金をしっかり確認しておきましょう。
確認項目
- 掃除する場所の優先順位
- どの程度キレイにするか
- 延長料金・交通費やオプション料金
ベアーズやキャットハンド等の派遣雇用型であれば、コーディネーター(社員)が事前訪問するので、綿密に打ち合わせすることができます。
ところが、タスカジやCaSy(カジー)等のマッチングサービスにコーディネーターはいません。
ですから、チャットや初サービスの際にハウスキーパーとしっかり打ち合わせする必要があります。
チップについてはこちら
≫ 家事代行業者のスタッフにチップは必要?【結論|必要なし】
掃除する場所を限定
掃除や片づけ、整理収納などは範囲(部屋の指定)を明確にしましょう。
理由は、範囲を限定すれば小さな変化にも気づけるから。
たとえば「水回り4点のみ」「玄関と1階の和室のみ」というように、掃除する場所を指定するといいですよ。
作業前に部屋の写真を撮る
掃除してもらう場所の写真を、事前に撮影しておくといいですよ。
なぜなら、掃除が終わってからだと掃除前の状態がわからなくなるから。
とくに細々したものが置いてある棚やクローゼット、テーブルの上などは必ず撮っておきましょう。
また、盗難だけでなく破損した場合の証拠にもなります。
事前に写真を撮るのはかなり有効です。
在宅する
家事代行サービス当日に在宅するという手もあります。
というのも、余計な心配をしなくて済みますからね。
もちろん、スタッフをずっと見ている必要はありません。
あなたは普段どおり過ごせばOK
(なかなか落ち着かないと思いますが 苦笑)
貴重品は金庫へ入れる
金庫を持っている人は貴重品をすべて中に入れておきましょう。
多くの家事代行サービスでも金庫の利用を推奨しています。
持ち運びやすい数千円クラスから、どっしり数十万円クラスの金庫がありますが、一つあると便利ですよ。
とくにどっしりした金庫が目に付く場所にあると、ガードの高さをアピールできるのでオススメ!
依頼する業者の数を絞る
依頼する業者はできるだけ絞りましょう。
なぜなら、業者数が多いと万が一盗難やトラブルに遭ったとき、犯人の見分けがつかなくなるから。
できるだけ1〜2業者に絞るといいですよ。
おすすめ家事代行はこちら
≫ 家事代行サービス10社を比較!実際に使ってみたおすすめランキング
スタッフは指名する
スタッフを指名するのも有効。
というのも、指名することでコミュニケーションが十分に取れるからです。
良い関係を築くことでトラブルを未然に防ぐことができますよ。
個人契約についてはこちら
≫ 家事代行・家政婦の個人契約はあり?依頼主・スタッフ目線で解説
防犯カメラを設置
あらかじめ「監視カメラ」を設置しておくのも効果的です。
そのワケは、万が一の時は動かぬ証拠になるから。
家庭用のそんなに高くない監視カメラでも、最近では高性能なものが多いです。
監視カメラを設置するなら必ず家事代行の了承を得る
監視カメラを設置する場合、必ず家事代行会社やスタッフ同意の上で設置しましょう。
スタッフからすれば、室内にいきなり監視カメラがあったらまるで信用されていないようで嫌な気分になりますよね。
家事代行の会社にかならず事前相談し「カメラがあってもOK」なスタッフを派遣してもらいましょう。
最初はお試しプランにする
いきなり定期契約するのではなく、最初はお試しプランで利用しましょう。
なぜかというと、スタッフとの相性やサービス内容を見極める必要があるから。
お試しプランは料金も安いので、可能であれば複数の業者に依頼してみるといいですよ。
そのうえで比較検討し、定期依頼に切り替えるのがベスト。
お試しプランのある家事代行はこちら
≫ お試しプラン(トライアル)のある家事代行サービス12社を比較
家事代行で盗難被害にあったときの対処法

では実際に盗難が発生した場合、どう対処すればいいのか見ていきましょう。
- 家事代行サービスの運営会社に連絡
- 消費生活センターに連絡
- クーリング・オフを利用
- 再発防止策を考える
- 警察に被害届を提出
家事代行サービスの運営会社に連絡
まずは、家事代行サービス会社に連絡しましょう。
伝えること
- トラブルの内容
- トラブル発生日時
- 写真や動画など証拠の有無
トラブルの内容を伝えたら、運営会社の返答を待ちましょう。
もし身の危険を感じるトラブルであれば警察に通報、そのあと運営会社に連絡すればOK
消費生活センターに連絡
はじめから消費生活センターや、国民生活センターに相談するのもアリ。
不信感を抱いてしまうと、家事代行サービス会社自体に相談したくない、という人もいるでしょうからね。
問い合わせ先は局番なしの「188」。
相談すると的確なアドバイスをくれますし、仲裁に入ってくれるので非常に心強い存在です。
クーリング・オフを利用
家事代行サービスはクーリング・オフが適用されます。
なぜかというと、依頼者が自宅で事業者と契約するのは「訪問販売」にあたり、特定商取引法が適用されるからです。
再発防止策を考える
今後も家事代行サービスを利用する場合、再発防止策を考えましょう。
具体的な方法は前項「家事代行の盗難・トラブル被害を未然に防ぐ方法」をご覧ください。
警察に被害届を提出
あまりにも悪質な盗難の場合、警察に被害届を提出することも検討しましょう。
盗難は「窃盗罪」という犯罪です。
場合によっては被害届を提出しないと、損害賠償の請求自体も困難になるケースもあります。
盗難被害にあわない家事代行業者の選び方

盗難被害にあわない家事代行業者の選び方は以下5つです。
- 料金設定が明確かどうか確認
- 大手に依頼
- スタッフの採用・研修体制を確認
- 損害賠償保険の有無・条件を確認
- 口コミや評価をチェック
料金設定が明確かどうか確認
業者の料金設定が明確かどうか確認してください。
なぜかというと、隠れた追加料金がないかチェックするため。
万が一、見ても分からない料金が記載されていたら業者に聞いてみましょう。
大手に依頼
「ダスキンメリーメイド」や「ミニメイド・サービス」などの大手に依頼するのも有効です。
大手に依頼するメリット
- 厳格なスタッフ採用基準
- 安心のサポート体制
- 充実の補償制度
「規模が大きい=100%安全」ではありませんが、安心感は格段にアップします。
「近くに大手家事代行サービスはない」という方は、できるだけ規模の大きな業者に依頼するといいでしょう。
スタッフの採用・研修体制を確認
あなたが依頼を検討している、家事代行サービスのウェブサイトから、スタッフの採用条件・研修体制をチェック!
そのワケは、スタッフの雰囲気や品質、会社の雰囲気がわかるから。
最近では家事代行サービスの需要も高まり、供給が追いついていません。
人材確保に必死な会社も多いです。
なかには、十分な研修を受けていないスタッフが現場デビューしているケースも。
そうなると必然的にトラブルも増えます。
そういった家事代行サービスを避けるためにも、スタッフの採用条件等は要チェックです。
ハウスキーパーについてはこちら
≫ 家事代行サービスのスタッフはどんな人?年齢層やタイプを徹底解説
損害賠償保険の有無・条件を確認
家事代行会社の損害賠償保険の有無・条件を確認しましょう。
というのも、保険内容や適用条件は会社ごとに異なるから。
また、家事代行マッチングサービスのなかには保険に加入していない会社もあります(原則、個人間の責任のため)。
万が一のためにも、事前にチェックしておくことをおすすめします。
口コミや評価をチェック
依頼前に業者の口コミや評価を検索しましょう。
依頼を検討している業者のウェブサイトではなく、SNSや口コミサイトなどをチェックしてください。
なぜなら、業者は自社のウェブサイトでデメリットを書かないからです。
まとめ|家事代行サービス依頼前に知っておきたい盗難対策

今回は、家事代行サービス依頼前に知っておきたい盗難対策について解説しました。
人間同士である以上、トラブルを100%防ぐことは厳しいです。
しかし、未然に防ぐ方法や正しい対処法を知っていれば焦る必要はありません。
いちばん大切なのは、スタッフとしっかりコミュニケーションをとること。
そうすれば、認識のズレや勘違いもなくなるでしょう。
今回は全体的にネガティブな内容ですが、家事代行は本当に便利でありがたい存在です。
まずは「お試しプラン」でサービスを体験してください。














